上司と部下が食事をしたときには、上司は食事代を出さないといけないのか?という疑問があります。
どういうケースでは奢る必要はなくて、どういうケースでは奢ることが普通なのか。上司の立場になると、その線引に悩むことがあります。
どうしたらいいでしょうか。理解することが5つ、試してみたいアクションが7つあります。
理解すること5つ
「必ず奢るべき」という決まりはない
上司が食事代を負担するのは文化や職場の慣習によるもので、法律や規則では決まっていません。
企業や業界、職場の雰囲気によって異なります。
「奢ることの意味」は状況による
部下を労う意味やモチベーションを上げるために奢ることもあるが、「おごる=偉い」という上下関係を意識させすぎると逆効果になることもあります。
部下の金銭的な負担を考えるかどうか
若手社員や経済的に厳しい立場の部下なら奢るのも一つの配慮です。
しかし、相手が十分に稼いでいる立場なら、奢る必要はあまりないと言えます。
場の目的によって奢るかどうかが変わる
例えば、「部下の慰労」や「歓迎会」のような場面では奢ることが多いですが、単なるランチや飲み会では割り勘が普通のケースも多いはず。
「毎回奢る」と負担が増え、期待されるようになる
たまに奢るのは良いが、毎回奢ると「上司が払うのが当然」と思われ、関係性が歪むことがあります。線引きを決めることが大切です。
試してみたいアクション7
以下の7個のアクションリストを参考にして、あなたの状況に合わせたアクションプランを練ってみましょう。
1.「目的」を明確にして奢るかどうかを判断する
例えば、「新入社員の歓迎会」や「プロジェクト達成の慰労」なら奢る。単なるランチや気軽な飲み会なら割り勘にする、など。
食事の目的で明確に線引きをしましょう。部下が明確な線引きをわかっていれば、奢られることを期待されません。
2.初めに「どうするか」を伝えておく
食事の前に「今日は割り勘でいこう」「今日は自分が出すよ」と明確にしておくと、気まずい空気を防げます。
奢るときには必ず前もって言うようにすると、言わないときは割り勘なんだなと伝わります。
3.奢るときには理由を付け加える
奢るときには、「今日は慰労を兼ねている飲み会だから自分が出すよ」というように、奢る理由を明確にします。
こうすることで、そういった理由のないときは割り勘だと部下に伝わります。
4.「半分負担」や「1杯目だけ奢る」など柔軟にする
フルで奢るのではなく、例えば「最初のドリンクは出すよ」「自分がちょっと多めに払う」など、柔軟な形で負担を調整する方法もあります。
部下が奢られることを期待しているような空気であっても、場の空気を壊さずに切り抜けることができます。
5.上司が奢るのが当然と思われないようにする
毎回奢ると「上司=奢る人」と認識されるので、「たまに奢る」くらいのバランスをとると良いです。
奢っていることが多いと感じたら、時には「今回は割り勘ね」と前もって伝えるようにしましょう。
そうすることで、奢ったときに「ありがとう」を引き出せる関係となります。
6.部下に選択肢を持たせる
ランチや飲み会に強制的に参加させるようにすると、部下は「無理して来た以上、代金は上司が出すのが当然」だと考えます。
ごく普通に、上司が「ランチに行こうか」と誘っただけでも、部下は断るのは難しいです。部下は強制された感覚を持ちやすく、上司が奢ることを期待します。
「これから私は◯◯にランチに行くつもりだけど、もし君も◯◯に行くつもりなら、一緒にいく?どうする?」と部下に選択肢があるような誘い方をしましょう。
断る選択ができるように常に配慮することで、「自分の意志で来たんだから割り勘で当然」という認識につながります。
7.割り勘を望むなら対等な関係にしておく
日ごろから「部下は私の言うことに従うべき。なぜなら私は上司だから」といった上下関係を強調していると、「上司は偉いんだから食事を奢って当然」という認識につながります。
「職場の役職はたまたま違っても、同じ対等の人間」として接していると、「割り勘でも当然」という職場の空気につながります。
割り勘が当たり前の職場を作りたいなら、意識して上司面を避けて、対等な関係を構築しましょう。
逆に、上司の威光を部下に見せつけて忠誠心を引き出したいなら、常に奢ることも一つの選択肢です。

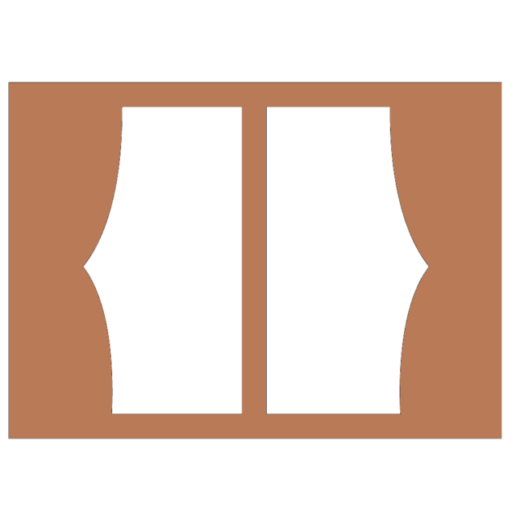
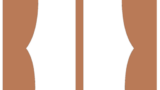
コメント
ログイン不要の掲示板です。メッセージをご自由にどうぞ!
(書き込みの反映までに最大24時間ほどのお時間をいただいています)