今やっている仕事がわからないことばかり。
上司には「質問しろ」と言われるが、「何がわからないのか」さえわかっていないことがある。
そんなときは、どうしたらいいでしょうか。理解することが5つ、試してみたいことが5つあります。
理解すること5つ
「何がわからないかわからない」のは珍しいことではない
新しい仕事や未経験の業務では、何をどう質問すればいいのかわからないのは普通のことです。
これは「理解力がない」ということではなく、単に経験が不足しているだけの状態です。
上司や同僚は「質問を前提にしている」ので遠慮しなくてよい
「わからないなら質問しろ」と言われるのは、上司や同僚も「最初からすべて理解できるはずがない」と考えているからです。
質問することは恥ずかしいことではなく、むしろ期待されている行動です。
「わからないことが整理できていない」状態は克服できる
問題は「わからないことをどう整理するか」にあるので、質問の仕方や情報の整理方法を身につければ、少しずつ解決できます。
初めから完璧に理解できなくても大丈夫です。
質問は「知識を得るため」だけではなく、「仕事を進めるため」にする
「すべてを理解しないと仕事ができない」と思うと焦りますが、実際には「次に何をすればいいか」さえ分かれば、仕事は前に進みます。
質問の目的を「すべて理解すること」ではなく「仕事を進めること」と考えると、気持ちが楽になります。
最初のうちは「質問の仕方」も学びながら進めていく
はじめのうちは質問が下手でも問題ありません。
むしろ、少しずつ質問の仕方を学びながら、「仕事の進め方」を覚えていくことが大切です。
試してみたいこと5つ
「とにかくメモを取る」習慣をつける
わからないことを整理するために、仕事中の言葉や指示をできるだけメモに残しましょう。
「何がわからないのか」をあとで振り返ることで、自分の疑問点が見えてきます。メモを取ることで、質問する内容も具体的になりやすくなります。
「何をすればいいですか?」と聞く習慣をつける
「何がわからないのかがわからない」場合は、「今の段階で自分がやるべきことは何ですか?」と聞くようにしましょう。
細かいことが理解できなくても、次に進むための指示をもらうことで、少しずつ仕事が進められます。
「質問のテンプレート」を用意しておく
うまく質問できない場合、以下のようなテンプレートを使うと、スムーズに聞きやすくなります。
「○○の作業をしているのですが、この後の手順がわかりません」
「○○について調べたのですが、どういう意味なのかよく理解できません」
「過去の資料を見ても、どこを参考にすればいいかわかりません」
このように「自分がどこで止まっているのか」を簡単に伝えるだけでも、相手は適切なアドバイスをしやすくなります。
一度やってみて、失敗してから質問する
完璧に理解してから進めようとせず、一度自分で考えながら進めてみるのも有効です。
「やってみた結果、ここでつまずきました」と報告すると、質問の内容も具体的になり、相手も助けやすくなります。
「1日の振り返り」をして、次に活かせる学びを増やす
仕事が終わった後、「今日はどこがわからなかったか?」「どんな質問をしたか?」を簡単に振り返る習慣をつけると、少しずつ理解が深まります。
質問がうまくできなかったと感じても、その経験を次回に活かせば成長できます。

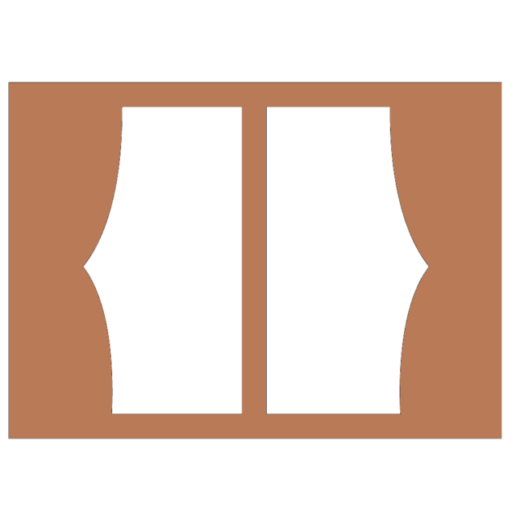
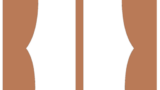
コメント
ログイン不要の掲示板です。メッセージをご自由にどうぞ!
(書き込みの反映までに最大24時間ほどのお時間をいただいています)